中津・宇佐・豊後・日田街道
(街道をゆく 第34回)
2005 10/4
司馬遼太郎は、『中津・宇佐のみち』を書くに当たり、中津と宇佐を訪れ、『豊後・日田
街道』を書くに当たっては、由布院と日田などを訪れて、風土などを実感されておられる。
「「とよ(豊)」
と口誦(クチズ)さむだけでも、野山が華やぎそうである。
野は周防灘に面し、帯状に東西にのびている。
背後(南)は深い山なみで、樹林が保水し、水を流し、野をうるおし、しかも天地異変
がすくない。まことに豊(トヨ)の国というほかない。」 と『中津・宇佐のみち』の「宇
佐の杜(モリ)」の章にある。
宇佐市を流れる駅館川であるが、隣の中津と合わせて中津平野と呼ばれていますが、沖
積平野で縄文中期には海であったところに駅館川の運んだ土砂で三角州が広かったところ
に思える。ただし、駅館川の右岸は山手からの尾根が宇佐市街地まで延びており、その東
は寄藻川の作った三角州のようである。かつては寄藻川沿いに深く海が入り込み、宇佐神
宮ののあたりまで深い入江をなしていたと地形からは思える。
図 1.大分県宇佐市周辺地形図

「私どもは、宇佐神宮の杜(モリ)にいたった。
まことに雄大な神聖森林で、まわりは堀にかこまれている。表参道を通り堀を見、かつ
朱塗りの橋を渡ると、大いなる朱塗りの鳥居の前に出た。
くぐると、池がある。この神は、池を好むのである。薦(コモ)神社のご神体が池であ
ることを思いあわせたい。池は、いうまでもなく、農業用の用水池を象徴するもので、築
堤能力を持つ秦氏の氏族的象徴でもあったのであろう。宇佐神宮の広い境内には「菱形の
池」というものがあるが、大鳥居をくぐってすぐ右の池は「初沢の池」というのである。」
と「宇佐の杜」の章で、述べておられる。ここの神事は寄藻川の河口の和間(ワマ)ノ
浜まで出て行くのだそうである。八幡神は朝鮮半島などからの渡来神と考えられており、
海から行ってきたルートを暗示しているように思われる。
気になる地名は下記のようである。
宇佐市 ウサ us 湾
寄藻川 ヨリモ iwor,i-mo 神々の住処の子供の川
駅館川を親川とみて、子供の川と言ったものと考える。"i" は母音の性質と同時に子
音の性質もあり、"y"に変わりやすく iwor,i →yori の変化は一般的である。宇佐神宮
の周辺が古代から神聖をおびた地であったことをこの川名は示しているように思う。
和間ノ海 ワマ wa-ma 岸辺の船着き場/澗
上記の地形図から、
桂 カツラ ka-tur 上手に延びている(尾根)
佐々礼 サザレ sa-sar 浜の草原
松崎 マツザキ matu-san-key 入り込んだ入江の前に出た頭、出崎
蜷木 ニナギ ni-nar-ke 高台の台地の所
ni-nar の語源は(ri-nar:高台の平坦の地、
台地)とあり、ri→ni はアイヌ語でも一般的。
青森 アオモリ a-o-mor,i 我らが川口/山裾の岡
和気 ワキ wa-ke 岸辺の所
江熊 エグマ e-kuma 太地の頭、山の横山
橋津 ハシヅ pa-usi-to/tu 山にくっついている海/峰
日足 ヒアシ pi-as-i 岩山が切立っている所
御幡 オバタ o-pa-ta 山裾の岡の所
尾永井 オナガイ o-na-ka-i 川口の水辺の上手の所
乙女 オトメ o-to(ko)m 川口の小山
吉松 ヨシマツ i-o-usi-matu 獲物がいつも群在する入江
時枝 トキエダ yuk-e-ta 突き出ている山の所
常徳 ジョウトク so-to-ke 岩礁の池の所
宇佐市に続く、中津市さらに行橋市まで、南西から東北の方向へ大小様々の川が流れ下
り、かつての古代の国「豊(トヨ)ノ国」があった。
豊ノ国 トヨ toy-o 泥だらけ
稲作文化を携えた弥生人にとって、このような土地が豊かな土地であったのであろう。
先生は中津では、先述のご神体が池である薦(コモ)神社とここの出身の福沢諭吉の旧
宅を訪れておられる。
図 2.福岡県中津市の周辺地形図

中津とは下記のような地名に思える。
中津市 ナカツ na-ka-to/tu 水辺の上手の海辺/峰
峰とは中津市の南の八面山の尾根に続く段丘が市街地の南から東にかけて延びているこ
とを示しているのであろうか。
地形図からその他の地名は下記のように思える。
吉富町 ヨシトミ i-o-us-to(ko)m,i 獲物がいつも多い小山
町の中央に天仲寺山と呼ばれる小高い岡がある。天仲寺というお寺もあるが、下記の地
名が先か、寺が先かは分からない。
天仲寺 テンチュウジter-chiw-us-i 踊る潮波の所にあるもの、岡
喜連島 キツレ key-tur 太地の頭、岬が延びている
恒富 ツネドミ tu-ne-to(ko)m,i 峰状の小山
今市 イマイチ i-ma
獲物が群在する
i-ot-i
獲物が群在する所
千束 チヅカ chi-(to)ska 我らが土手
列状に池が点在し、かつて大川がこの付近を
流れていたのであろう。
野田 ノダ nota 太地のホホ(山尾根のふくらみか?)
nutap 川の湾曲部(かつての川の湾曲部?)
別府 ビョウ pi-o
小石が群在する/小石の川口
孝子 コウジ ukaw-us-i 石が重なり合っている場所がある所
宇野 ウノ us-not 湾の太地のアゴ、出崎
徳並 トクナミ tok-na-muy 突き出ているもの、出崎の水辺の入江
土佐井 トサイ to-sa-i 海の浜辺の所
山手の方にもかつての海岸線を思わせる地名がならんでいるように思える。
万田 マンダ oman-ta 奧に入った所
相原 アイハラ ay-par イラクサの川口/広い所
永添 ナガゾエ na-ka-so-e 水辺の上手の岩の山/岩礁の入江
かつては山国川の流れが左折せずに真っ直ぐ
流れていたようで、この廻りに池が連なる。
加来 カク ka-kut 上手の岩崖
大貞 オオサダ oho-sa-ta 奥深い浜の所
田尻 タジリ ta-sir,i 切立った土地/山(海岸段丘の場所)
定留 サダノミ sa-ta-not-muy浜の切立った太地のアゴ、出崎の入江
犬丸川 イヌマル inun-mak-ru
漁に滞在する奥まった道(のある川)
今津 イマヅ i-ma-to 獲物が群在する海辺
植野 ウエノ wen-not 悪い出崎
野依 ノヨリ no-iwor,i 良い神々の住処
野依と植野と相反する対の地名に思える。
古代人の狩猟生活に関わる地名であろうか。
是則 コレノリ kor-no-ri 支配する(非常に?)良い高台
諸田 モロタ mor-ta 岡の所
伊藤田 イトウダ etu-o-ta 太地の鼻、出崎の裾の所
詳細地形図では手の指のような出崎があり、
その麓に伊藤田集落がある。
なお、山国川の上中流域が有名な耶馬溪(ヤバケイ)の渓谷である。
こちらが日向街道などの豊前(ブゼン)のみち、に対して豊後(ブンゴ)街道を別府の
北から鶴見岳、由布岳の南を抜けて、由布院に入り、久住(クジュウ)まで、それから日
田往還を日田(ヒタ)まで行かれており、順次見てみよう。
別府、由布院は温泉町である。由布・鶴見火山群と呼ばれる地熱エネルギーが由布岳・
鶴見岳の側面にある由布院と別府の地に豊富な湯を供給しているのだそうである。
別府の地名は別府市の南の大字別府朝見、乙原地区などから広がったと考えられている。
図 3.大分県別府市大字別府周辺拡大地形図

朝見川、乙原川の交わる川口など別府地名にぴたりと合うと考える。
別府 ベップ pet-put,u 川の口、川尻
乙原 オトバル o-tok-par 山裾を突出した川口
朝見 アサミ as-muy 切立つ入江
由布院という観光地が成り立ったのは、核となるビジョンがあり、大正時代に外部の風
を取り入れ、徹底した町作りの骨格とビジョンを造りあげたからと先生は言われている。
「牛一頭牧場運動」など、都会の人に子牛を一頭ずつ買ってもらい、地元の農家が飼育
し、牧場の衰退を防いだ例など、「理想の温泉地」としてビジョンの下敷きがあったから
成功したのだそうである。先生は由布院に泊まられた宿の感想を
「雑草までが当主の思想にくるまれているのではないか」
と表現されている。
図 4.大分県大分郡湯布院町の周辺地形図

湯布院町、由布岳などのユフ地名について、下記のように考えてみた。
由布院/岳 ユフ yu-p 湯の所
i-up その(神の)オデキ
i-up(sor) その(神の)フトコロ
yu-p は最も一般的であろう。由布岳の頂上付近の噴火は比較的新しい(2000〜
1500年前頃)と言われており、この山の廻りに8個の側火山があり、それらが大きくな
る過程をを i-up と言ったと考えてみた。また、「木綿(ユフ)」はコウゾの木皮から
紡いだ糸の古語であり、古代の麻布に比べて、この糸で紡いだ服は暖かく、この地がその
産地で i-up(sor) の地名が出たと推定してみた。
その他の気になる地名は下記のようである。
福万山 フクマ hur-kuma 岡の横山
若杉 ワカスギ wakka-su-ke 水辺の鍋底状の窪地の所
飛岳
トビ top,i 根曲り竹状(の山)
この山名はその他、福岡、長崎、熊本県にあ
る。「飛び離れている山」の弥生系かも知れ
ない。
津江 ツエ tu-e 山峰の(下の)入江
石松 イシマツ pi-us-matu 小石が群在する入り込んだ入江
平 ヒラ pira 崖
徳野 トクノ tok-not 突き出た太地のアゴ、出崎
槐木 ニガキ ni-ka-ke 木々の上手、岡の所
津々良 ツヅラ tu-tur 峰が伸びている
寺川 テラゴ ter-ko 流れの踊る、滝川の所
渡司 ワタシ wattar-us-i 流れの絶えない淀み、淵にある所
星岳 ホシ ho-us-i 山裾にくっついているもの、山裾の山
平石 ヒライシ pira-us-i 崖にある所
山崖の急勾配の下の地に集落がある。
長野 ナガノ na-ka-not 水辺の上手の太地のアゴ、出崎
ここの「野」は原場とはほど遠い地である。
先生は由布院から日田へゆく途中で豊後街道を九重(ココノエ)町を経て、久住(クジ
ュウ)山を見に行かれている。「クジュウ」をめぐり、九重山か久住山か、300年間争わ
れ、総称を九重山とし、単独の山を久住山として決着したのだそうである。なお、「クジ
ュウ」の地名に対しては大友幸男先生は下記のように言われている。
九重/久住山 クジュウ kus-ru 越える道
旅の目印の山当ての地名。
「豊後日田は、江戸期では三万二千石、堂々たる天領の地であった。土地ではヒダといわ
ず、ヒタと澄む。
「日田は、水郷です。」
と、由布院の宿の女中さんがいったが、この場合も、関東の潮来(イタコ)のように「水
郷(スイゴウ)」とは言わない。スイキョウという。
日田は高原をなして、いわば僻地というにちかいが、江戸時代は漢学がさかんで、広瀬
淡窓の感宜園(カンギエン)などは全国からこの遠国(オンコク)のそのまた不便な高原
の町に子弟が集まり、門人三千人といわれた。江戸期における慶応、早稲田といった私学
の雄は江戸よりもむしろこういう土地にあったということが、江戸体制を考える上で興味
がある。
スイキョウなどという音(オン)も、この町に漢学書生が充満していたのと無縁ではあ
るまい。漢学者は、坊主よみといわれる呉音(郷の場合はゴウ)を卑しみ、漢音のキョウ
をとるのである。」 と「天領・日田郷」の章にある。
大分は名門大友氏の大友宗麟(ソウリン)の野望を島津氏に砕かれ、滅亡の一方をたど
り、豊臣、徳川政権にかけて、多くの大名配置変えの後、幕末期には八つの藩と七つの天
領などに分割されている。悲劇というべきか、その代わりに競い合う個性豊かな地域とし
て、日田郷もあったのであろう。
図 5.大分県日田市周辺地形図

日田市の「ヒタ」地名は下記にピッタシである。
日田市 ヒタ pitar 小石原
日田市の北西の隣村は福岡県朝倉郡小石原村であり、ヒタが縄文地名であるのに対して、
小石原は弥生語の同じ意味の言語の異なる双子地名をなしている。飛騨高山などのヒダと
同一地名であろう。飛騨山脈などのヒダの pitar の pi は岩山かも知れない。
語源を (pi-tar:小石原/岩山が踊っている) と推定してみた。
その他の気になる地名は下記の通り。
阿蘇山 アソヤマ as-so-ya-oma 切立つ辺り一面の山縁にある
山でない字名である
三日月山 ミカヅキ muy-ka-tuk-i 入江の上手に突出したもの、山
この地名も下記のようにあり、上記の地名解釈に合っている。
表 1.各地の三日月山の分布
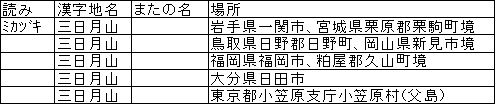
杷木山 ハキヤマ pa-ke-ya-oma 太地の頭、山の所の山縁にある
ここも山でない字名である。ここは杷木町。
三春 ミハル mintar 神々の庭
この種の地名に三原、美原、三田(ミタ)、新張(ミハリ)など、古代の狩猟場の地名
を示しているようである。
夜明 ヨアケ i-o-arke 獲物の多いもう一方の所
高井岳 タカイ ta-ka-i 切立った上手の所
白土 シラツチ sirar-tu-us-i 岩の峰にくっついているもの、所
宮 ミヤ muy-ya 入江の山縁
田篭 タゴモリ tapkop-mor,i タンコブ状の岡
君迫 キミサコ kim-sa-ko 山の前に出た所、出崎
吹上 フキアゲ pu-ke-arke 倉、獲物の多い所のもう一方の所
倉とは80-90mの砂浜上に119mの丸く
こんもりと小さい岡、月隈山があり、この
形を言っているかも知れない。日田藩六万
石の月隈城跡の所である。
中村 ナカムラ na-ka-mur 水辺の上手の岡
三和 ミワ muy-wa 入江の岸辺
花月 カゲツ ka-key-tu 上手の山の峰
尾当 オトウ o-tu-o 山裾の峰の麓
諸留 モロドメ mor-to-muy 岡の(下の)沼の入江
有田 アリタ ar-ta もう一方の所
天瀬町 アマガセ am-kas 爪状の岡の上を越す
大宮 オオミヤ oho-muy-ya 山奥の入江の陸岸
赤米田 トバシタ topa-si-ta 沼頭の大きな所
日田市街地がかつて沼であった頃、そこに逆三角形上に突き出た岬であったことを言っ
ているように思えるが、読めない地名である。
荒平 アラヒラ ar-pira もう一方の崖
銭花 ゼニバナ sempir-pana 日影の花、出崎
渓谷の東に川に沿い山崎が突き出ている。
串川 クシゴ kusi-ko 対岸の所