オホーツク街道
(街道をゆく 第33回)
2005 9/28
北海道にはアイヌ文化とは別種のオホーツク文化が入っていたとして、司馬遼太郎は『オ
ホーツク街道』を著わし、そのため、北海道の東北海岸沿いを稚内から網走などを経て、
知床半島まで旅されている。
オホーツクとはシベリヤ東部のツングース諸語語で「広い川」を意味する、"okata"、
"okhota"等に、ロシア語の語尾"sk"が追加され、"okhotsk"となったものだそうで、広
い川とは現在はロシア、中国の国境をなす、「アムール川(黒竜江)」のことであろう。
今回は『オホーツク街道』の足跡を訪ねて、本格的なアイヌ語地名を辿ってみよう。
先生は旅の結論を下記のように、
「知床オホーツク沿岸の考古学遺跡はにぎやかで、斜里町から半島の先端にいたるまでわ
ずか七十キロメートルほどの沿岸に、こんにちわかっているだけで八十二カ所もの遺跡が
ある。遺跡銀座のようなものである。
そのほとんどが、縄文早期から続縄文時代のもので、さらにいえば、縄文文化ほど、日
本固有の文化はない。
この固有性と、オホーツク文化という外来性が入りまじっているところに、北海道、と
くにのオホーツク沿岸の魅力がある。」と『オホーツク街道』の「旅の終わり」の章で述べ
ておられる。
サハリン(樺太)から網走、知床に至る海の道があり、そこをツングースの一派が渡っ
てきたことを発見したのは、E.S.モース、坪井正五郎、鳥居龍蔵などの学統を受けつ
いだ、米村喜男衛(キオエ)という、理髪職人をしていた人であったそうである。大正2
年、まだ21歳の頃、寒村であった網走に移住してきて、網走川河口の近くの砂丘に、古
代人の人跡、モヨロ貝塚を見いだしたのだそうである。
「米村喜男衛が棒の先でそっと崩してみると、貝類のほかに、石器、骨角器、土器などが
出てきた。やがて人骨もでる。どれもが、他に類例をみないものだった。
日本史学に、”オホーツク人”が登場する瞬間である。」 と「韃靼の宴」の章で、感
慨深げに述べておられる。
稚内市の裏山に登れば、天気の良い日には樺太が北に見える。学校を出たての若かりし
頃、稚内に二ヶ月を過ごした、思い出である。幕末に外国船が頻繁にあらわれだした頃、
樺太は大陸につながっていると海外でも信じられていた。海防の必要におられた江戸幕府
は間宮林蔵を樺太探検に使わし、樺太が島であることを、間宮海峡を発見している。
図 1.北海道稚内市周辺地形図
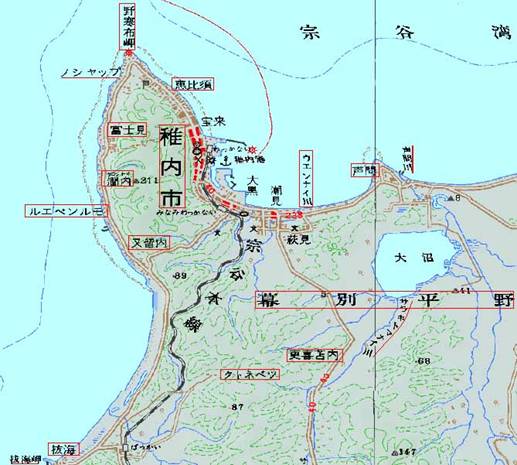
稚内はノシャップ岬の東岸の道に沿って細長く延びた町である。訪れた当時、ミニスカ
ートが流行っており、極寒の時でも娘さんがミニスカート姿で、足もとを取られながら歩
いておられたのにはビックリさせられた。
稚内は下記の地名である。
稚内市 ワッカナイ (yam-)wakka-nay (冷たい)水の川
フシコ・ヤムワッカナイ、(husko:古い;もとの)という川に鮭(サケ)が寄ってきて、
人々が集まってきたのが起源と言われている。後に樺太航路の拠点として大発展し、その
後漁港で栄えている。
幕別平野 マク(ン)ベツ mak-un-pet 後(山の方)にある川
野寒布岬 ノシャップ not-sam 太地のアゴ、岬のそば
m→p の変化は不破裂音で一般的らしい。
根室半島の先端の納沙布(ノサップ)に同じ。
富士見 (明らかに和語であるが西に利尻富士を見れる位置を示して入る。
元々は次の通り。)
ニヲトマリ ni-o-tomari 木々が群生する船泊
濶内 ウロンナイ ur-o-un-nay 岡の裾にある川
この地名は「アイヌ語ではあるが意味不明」とある。詳細地形をみると海岸段丘の下段
の段丘集落であり、尾根間の川があった痕跡もある。勝手に解釈してみたが。ここの南に
カタカナのままの地名が、「ルエベンルモ」、「マタルナイ」、「ルエラン」と続く。手持ち
の資料で行き当たらなかったので、次のように推定してみたが。
ルエベンルモ ru-e-pen-rum 道がそこから川上の(にある)太地
の頭、山/岬
又留内 マタルナイ mata-ru-nay 冬道の川
東から流氷のない西海岸に冬場移動したので
あろうか。
ルエラン ru-e-ran 道がそこから下る
集落のすぐ東の峠を越えるとクエラン川があ
り、稚内市に流れ込む。
クエラン川 ku-e-ran 我らがそこで(坂を)下る
ルエランと対の地名であろう。
地形図の地名に戻る。
抜海 バッカイ pakkay-pe 子を背負うもの
海岸の岩の形がそのように見える。
恵比須 エビス e-pis-ne 山頂/水源が浜/尾の方にある
各地にあるエビス地名と地形が同じと考えた
が、もう一つはっきりしない。恵比須地域に
2軒の神社を確認したが、神社名不明。
ウエンナイ川 wen-nay 悪い川
なぜ悪い川なのかまでは見いだせなかった。
鮭が遡上しない川だったのでは。
声問 コエトイ koy-toye 波を切る/波が崩れる
声問川、声問岬があり、地形に関わる地名。
更喜苫内 サラキトマナイ sarki-to-oma-nay カヤ/アシの沼にある川
讃岐国の「サヌキ」はもともと「サルキ」で
あったと言われており、(sar-ki:湿原のカヤ)
のこれであろう。
クトネベツ kut-ne-pet 岩崖である川
「私どもは宗谷湾に沿って北上し、最北端の宗谷岬にむかっている。このまま走ればーー
海に道路があればーーあと一時間で樺太につくはずである。
”オホーツク人”たちは、樺太からやってきた。」 と「宗谷」の章でのべられ、素朴
民族として、ギリヤーク(いまはニブヒ)として、日本人、アイヌ人へ最も近いことを述
べられている。その他、近隣の民、鮭の漁皮で服や靴を作るナナイ族、樺太でトナカイを
飼ったり海獣漁をするウイルタ族(旧はオロッコ)、エベンキ族、エベン族などとの民族
のつながりに気を配られている。
図 2.北海道稚内市の宗谷岬周辺地形図

以後、和語により着けられ、もとの形が鮮明のものは楕円の赤丸で示した。
宗谷岬 ソウヤ so-ya 岩/岩礁/滝の陸岸
この地名はソウヤ(宗谷、曽屋、惣谷)、シオヤ(塩屋、塩谷、東入)、ショウヤ(庄
屋、勝谷)等と、北海道以外でも多く、神戸市垂水区の塩屋町などもこれであろう。
珊内 サンナイ san-nay 流れ下る川
この地名も青森の三内丸山遺跡、秋田県平鹿郡山内(サンナイ)村などと同じであろう。
大水が出る地名にあると言われているが、島根県大田市等に跨る三瓶山、三瓶川なども
この、”san-pet”であろう。
清浜 キヨハマ (かつては下記のようで、和語に翻訳した地名)
ピリカタイ pirka-tay 美しい林
富磯 トミイソ (かつては下記の地名)
リヤコタン riya-kotan 越年する村
増幌川 マシホロ mas,i-uppo カモメの輪唱歌
カモメが鳴きながら群れ飛ぶ姿をたとえたも
の。mas,i-uppo→masihoro 音韻変化。
泊内川 シマリナイ tomari-nay 船泊を流れる川
目梨川 メナシ menas,i 東風
峰岡 ミネオカ (かつては下記の地名)
トキマイ/トキマエ tuki-oma-i/tuki-mo-iwa
酒椀があるもの、所/酒椀の小山
時前川が流れている。
萌間山 モエマ/モイマ mo-iwa 小山
mo-iwa→moima
宗谷岬から宗谷国道と呼ばれる国道238号線を南東へ約30Km進むと猿払村浜鬼志別
へ達する。ここにはインデギルカ号遭難者慰霊碑があり、碑文には次のように書かれてい
る。
『昭和14年12月12日。ソ連船「インディギルカ」号とそれに乗り合わせていた人
々に最後の時がやって来た。
「イ」号は、秋の漁場を切り上げて帰る漁夫及びその家族1004名を乗せて、カムチ
ャッカからウラジオストクに向かって航海中、折からの暴風雨に押し流され、乗組員たち
の必死の努力も空しく、進路を失い、12月12日未明浜鬼志別岩沖1500mのトド岩
に座礁転覆、700余名の犠牲者を出す海難史上稀有の惨事となった。
身をさくような厳寒の海上で激浪と斗かい、肉親の名を叫び続けながら力尽きて死んで
いった人々のことと、その救助に全力を注いだ先人たちの美しい心情は、人類のある限り
忘れてはならない。
この碑は、北海道はもとより国内の数多くの人々、並びにソ連側の海員、漁夫の善意に
基く浄財によって、「イ」号と運命を共にした人々の冥福を祈ると共に、国際親善並びに
海難防止の願いを込めて建立されたものであり、台座の石はソビエト社会主義共和国連邦
から寄贈された花崗岩である。』
当時は国際情勢も風雲急を告げる状況にあり、ノモハン事件後で、満州事変なども始ま
り、ソ連との関係は最悪の状態であり、冬場の嵐と格闘しながら救助活動をしたが、イン
ディギルカ号の悲劇として語り継がれている。
図 3.北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別周辺地形図

座礁転覆したトド岩とは図中の海馬(トド)島である。
地名は下記の通り。
頓別平野 トンベツ to-un-pet 沼にある(入る)川
猿払村 サルフツ sar-put,u 湿原の川口
知来別 チライベツ chiray-pet イトウ魚の川
幻の大魚、イトウの生息地である。
シネシンコ sine-sunku 一本のエゾマツ
一本松という所であろう。
鬼志別 オニシベツ o-ni-us-pet 川口に木々が群生する川
北海道以外にも「オニ」地名は多く、鬼(越、王、屋、丸、原、古賀、高、崎、鹿、取、
首、瀬、石、袋、沢、池、長、津、伏、木、柳、脇、塚など)、小入谷(オニュウダニ)、
遠敷(オニュウ)、尾西(オニシ)なども上記の "o-ni-us" を伝えるものが多いので
はないだろうか。
豊里 トヨサト (もとは字、鬼志別)
恵山辺 エサンベ e-san-pe 頭が前に出ているもの、岬
猿骨 サルコツ sar-kot 湿地の窪地
sar-e-ukot 湿原(川)がそこでくっついている
芦野 アシノ (かつては下記の地名)
サル sar 湿原、葦原
キモマ沼 kim-oma-to 山にある沼
ホロ沼 poro 大きい
知里真志保先生はこの語の語源は
(po-nu:子を持つ)からとされている。
猿払 サルフツ sar-put,u 湿原の川口
狩別 カリベツ kari-pet 曲がっている川
カムイト湖 kamuy-to 神の沼
さらに南東に進むとすぐ、浜頓別町のクッチャロ湖を右手に見て、枝幸町の神威岬を越
える。
図 4.北海道枝幸郡浜頓別町と枝幸町境の神威岬周辺地形図

この地形図のすこし右下に枝幸町の中心地があるが、かつてコールドラッシュに沸いた
町だそうである。
クッチャロ湖、枝幸町の地名は下記のようである。
クッチャロ湖 (to-)kutcharo 湖のノド
阿寒の屈斜路湖も同じである。
枝幸町 エサシ e-sa-us-i 頭が浜(前)についているもの、岬
檜山のかつてのニシン漁で有名な江差町、岩手県の江刺市などこの地名であろう。
地形図からは下記のように解釈されている。
神威岬 カムイ kamuy-etu 神様の岬
人が近づいてはならないような危険な場所に
"kamuy"などと名付けたのだそうである。
宇曽丹 ウソタン u-so-ta-an-pet 互いに滝を掘っている川
us-ta-an-nay いつも掘っている川
ここで砂金ブームが明治末に起きたそうで
る。
珠文岳 シュブン supun ウグイ魚(石斑魚)
斜内 シャナイ so-nay 滝の川
目梨泊 メナシ nenas,i 東風
問牧 トイマキ tuy-pake 崩れた頭、岬
toy-mak 土の後
野近志 ノチカシ not-ika-us-i 岬をいつも越える(迂回する)所
枝幸町からさらに、雄武(オウム)町、興部(オコッペ)町を経て紋別市にいたる。途
中にも興味深い地名が多いが、上記の町名のみに限定すると
雄武町 オウム o-mu 川口が塞がる
オウム川の河口を風や潮流が砂で塞いだこと
による
興部町 オコッペ o-ukot-pe 川口をつけ合っているもの
かつては興部川と藻興部川とが川口で合流し
ていたのだそうである。
紋別市は古く、オンネノトロ、トマリ、ノトロなどとも呼ばれていたそうであるが、「モ
ンベツ」は下記地形図に元紋別の地名があるように、藻鼈(モベツ)川に因む地名である
そうである。
図 5.北海道紋別市周辺地形図

紋別市 モンベツ mo-pet 静かな川
藻鼈川 モベツ mo-pet 静かな川
川口近くの流れは遅流であることによる川名
沙留 サルル sar-oro 湿原の中(の川)
思沙留川 オムサルル o-mu-sar-oro 川口が塞がった湿原の中(の川)
この川の河口はオムシャリ沼に流れ込んでおり、オムサロと呼ばれる原生花園や遺跡が
続いてあり、上記の地名解釈と同様のものであろう。
富丘 トミオカ (かつては下記の地名)
オムサル o-mu-sar
川口が塞がった湿原
渚滑 ショコツ so-kot
滝の窪地
渚滑川、渚滑岳とあり、上流に滝上町があり
もともとはこの辺りの川名からであろう。
ウエンヒラリ岬 wen-pira-ri 悪い崖の高台
さらに南東へ、湧別町、オホーツク海へ続く、サロマ湖を左手に見ながら湖畔を走り常
呂町を経て、能取湖畔を左回りに半周して網走市へ出る。
湧別町 ユウベツ yu-pet 湯の川
yupe(-ot) チョウザメ(が群生する)
ipe-ot-i 食べ物(魚)が群生する所
湧別川の地域は有名な地名が多いが、地名の語義の分からなくなったものが多いのだそ
うである。山田秀三先生も湧別町の地名は保留されている。古くユウベチ、ユウヘツ村。
サロマ湖 sar-oma-to 湿原ある沼
常呂町 トコロ tu-kor 峰、山崎を持つ
to-kor 沼を持つ
この地名も山崎説と沼説と大きく揺れた地名
であるらしい。山田先生は古い文献では「ツ
コロ」とあるのに注目し、tu→to の音韻
変化はないとし、山崎説を取っている。
能取湖 ノトロ not-oro(-kotan)岬の所(中)の村
能取の集落名から湖の名前になった。
能取湖、網走市の周辺地形は下記のようである。
図 6.北海道網走市周辺地形図

網走市のアバシリ地名も、アイヌ語の語義が薄れると共に諸説が生じ、諸説粉々とある
そうであるが、主なものは下記の通り。
網走市 アバシリ a-pa-sir,i 我らが見つけた土地
a(=chi)-pa-sir,i 祭場の土地
apa-sir 雨漏りのする場所(洞窟)
古い記録には「ハハシリ」、「ハバシリ」とあるそうであるが、現地の伝承ではもとも
と「チバシリ」で、知里真志保先生は、
「チバはイナウサンの古語で、チバシリは、幣場の島、と解すべきでもともと網走川の海
中にあった帽子岩についた名称である。この岩は古くカムイ・ワタラ(神・岩)といわれ、
漁民であるアイヌが崇拝する沖の神の幣場であった。チバシリが古語であり、意味が分か
らなくなってきてアパシリに変わりこの土地の地名になった。」
とされ、これが正しいのではないだろうか。
千葉県にはチバ地名と、かつての安房(アワ)国、これは "a-pa" から出たものと考
えるが、「チバ」、「アパ 」の組み合わせがあり、四国の阿波(アワ)国 などもこの祭場
地名であろうと考えている。また、(a:我らが)のつく地名、アタゴ(a-tapkop:我らが
タンコブ山)、アヤ(a-ya:我らが陸岸)、アオ(a-o:我らが川口)、(a-wa:我らが岸辺)
などいずれも祭場に関係する地名に思える。
その他、地形図から下記のような地名であろう。
美岬 ミサキ (元の字名は最寄村で、下記のようであろう。未確認)
モヨロ moy-oro 入江の所
駒場 コマバ (元の字名はフシコタンで、下記であろう。未確認)
フシコタン husko-kotan 古い村
リヤウシ湖 riya-us-i いつも越年する所(越年村に由来)
卯原内 ウバラナイ u-par-ray 互いに川口が死んでいる(口なし川)
opar-ray 川口が死んでいる(口なし川)
o-para-nay 川口が広い川
決め手のない地名の一つ。
冒頭に述べたように米村喜男衛が見つけたオホーツク人の遺跡は網走川の河口の左岸の
モヨロ(最寄)遺跡であった。
最後は世界遺産となった知床半島の斜里郡斜里町のウトロである。
図 7.北海道斜里郡斜里町ウトロ周辺の地形図

下記のような地名である。
知床半島 シレトコ sir-etok,o 太地の頭の突出部、突端
斜里町 シャリ sar,i 湿原、草原
宇登呂 ウトロ utur,u-chi-kus-i その間を我らが通る所
岩と岩の間を通る、交通の難所であったらしい。(chi-kus-i:我らが通る所)とは何の
変哲のない言い方であるが、交通の難所を言ったらしい。これで思い出すのは古事記に筑
紫(チクシ)島と出てくるかつての筑紫国、福岡平野のことである。ここが古代において
交通の難所であったのは、ここの平野においては幾本もの大河がおもに南から北に注ぎ、
橋の無かった古代においては、東西に移動するには大潮の干潮時の川底が現れ、砂丘状態
になった時を見計らい、四つんばいになりながらも渡ったということだったのではないだ
ろうか。まさに "chi-kus-i" だったのであろう。
地形図のその他の地名は下記のようである。
サシルイ岳 sas-ruy 昆布が烈しい、群生している
この山の東を流れるサシルイ川に由来。
羅臼岳 ラウス ra-us-i 低くあるもの、所
百名山にも指定されている山名としては相応
しくなく、羅臼川、羅臼集落からアイヌ地名
の分からない和人が名付けたのは一目瞭然。
元々の山名は下記の通り。
チャチャヌプリ chacha-nupri 親父の山、大山
知西別岳 チニシベツ chip-ni-us-pet 舟の木が群生する川
(知西別川に由来)
岩尾別 イワオベツ iwaw-pet 硫黄の川
ホロベツ川 poro-pet 大きな川
チャシコツ崎 chasi-kot 砦の跡/祭場の跡
フンベ川 hunpe 鯨(クジラ)
この川の川口の出崎が鯨の形であろうか。(hunpe:鯨)の語源を (hur-pe:岡のよう
なもの) と考えたがどうであろうか。各地に フンペ/フンベ地名はあったそうである
が、宇部市などのウベ地名も同じであろう。ここには中宇部、上宇部、沖宇部などの字名
があり、鯨のようなこんもりした岡を確認したのだが。
オショコマナイ川 o-so-ko-oma-nay川口の滝がそこにある川
未確認。
オシンコシン崎 (岬の付け根にある、南側のオシンコシン滝からきた
岬名。しかしこの滝川名はもともとチャラセナイであ
った。岬の東に小川があり、オシンクウシ川があり、
この名前がオシンコシンとなまって滝名になってしま
ったらしい。)(これらの川名は下記の通り。)
オシンクウシ川 o-sunku-us-i 川口にエゾマツが群生するもの、川
チャラセナイ川 charase-nay チャラチャラと音を立てる川
遠音別 オンネベツ onne-pet 大きい川
日本人、アイヌ人はどこから来たか、アイヌ人・アイヌ文化の北方との関連をとなえる
人も多い。オホーツク人の到来、オホーツク文化の到来は、アイヌ人・アイヌ文化にどの
ように働いたか、回答が待ち遠しい限りである。