伊那街道 三河・信濃
一部修正2004/10/20
2004 3/25
伊那谷を貫いて三河と南信濃を結んだ交易の道である。東海道の宿駅吉田は現在の豊橋
市であり、豊川を遡り、途中の飯田からは天竜川に沿って遡り松本まで約220Kmの道
程である。戦国時代の武田信玄や織田信長、徳川家康なども利用した軍事路でもあったそ
うである。飯田領主による宿駅が設置されると中山道の脇往還としても発達し、おもに物
資輸送に利用され、「中馬(チュウマ)」と呼ばれる荷物輸送が盛んになったそうである。
豊川の川口にあり、江戸と京を結ぶ東海道のほぼ中間の吉田宿(現、豊橋市)は三河の
要衝として栄え、そこから御油宿が置かれた豊川を経て新城宿へと続く。
図 1.愛知県豊橋市、豊川市周辺地形図

豊川の川口の吉田はアイヌ・縄文語の立場から見れば下記のような地名であろう。
吉田宿 ヨシダ i-o-si-ta 獲物がとても多い所
豊川 トヨ toy-o 泥だらけ
その他気になる地名は下記のようである。
豊橋市 トヨハシ toy-o-pa-us-i 泥の川口が山辺にある所
御津町 ミト muy-to 入江の海
御馬 オンマ o-un-moy 川口にある入江
佐脇 サワキ sa-wa-ke 砂浜の岸辺の所
小田淵 オダブチ ota-put,i 砂浜の川口
伊那 イナ inaw 幣場、祭場
瓜郷 ウリゴウ hur,i-ukaw 岡の石の重なり合いの地
*清洲 キヨス key-o-su 太地の頭、出崎の川口の窪地
(干拓地とのご指摘)
吉川 ヨシカワ i-o-si-ka-wa 獲物がとても多い上手の岸辺
牟呂 ムロ mur-o 岡の裾
*神野 カミノ (明治期に神野(カミノ)金之助が開発した干拓地)
*三郷
王ヶ崎 オウガサキo-u-ka-san-key 川口がくっつき合う上手の出崎
麻生田 アソウダ as-so-ta 切り立つ辺り一面の所
豊川を登ればいよいよ山間部という辺り。
賀茂 カモ kan-moy 上手の入江
kamuy 神の所
小野田 オノダ o-nutap 川口の川の湾曲部
森岡 モリオカ mor,i-okay 岡が群在する
岩手県盛岡市のモリオカと同じでは。
図 2.愛知県豊橋市森岡を西から眺めたカシバード撮影像

金田 カネダ kan-nay-ta 上手の川の所
キンダ kim-ta 山の所
読み方が分からないが双方成り立つが。
小鷹野 オダカノ o-ta-ka-nup 山裾の切り立った上手、岡の原場
多米 タメ ta(ko)m-e 小山の頭、頂上
三河への入口にある新城宿、新城市であるが、海への出口を求める戦国の雄、甲斐武田
勝頼軍は徳川家康が家臣奥平信昌(ノブマサ)の守る長篠城を包囲し、織田信長はこの地
設楽原(シタラガハラ)に出陣し、精強を誇る武田騎馬軍団を迎え撃つことになる。3千
丁の鉄砲による近代戦は武田軍を一気に壊滅させ、その後武田氏は滅亡の一途をたどるこ
とになってしまった。
図 3.愛知県新城市周辺地形図

気になる地名は下記の通り。
宝飯郡 ホイ ho-i 山裾の所
新城市 シンシロ sir-(no)-sir-o 太地の尊い山裾
白鳥 シラトリ sirar-tur-i 岩盤が伸びている所
荒原 アワラ apa-ra 我らが岡(祭場)/入口の低い所
田代 タシロ ta-sir-o 切り立った山の裾
見代 ミシロ muy-sir-o 入り込んだ所の山の裾
ミダイ muy-tay 入り込んだ所のの林
読み方が分からないが双方成り立つが。
本宮山 ホングウ (山麓に砥鹿(トガ)神社があるがその本宮の意らしい)
砥鹿 トガ tu-ka 峰の上手
横川 ヨコガワ yoko-ka-wa 獲物を狙う上手の岸辺
長篠 ナガシノ na-ka-sinot 水辺の上手で遊ぶ所/祭りする所
大海 オオミ o-u-muy 川口がくっつき合う入江
八束穂 ヤツカホ ya-toska-ho 山縁の土塁の裾/川口
有海 アルミ ar-muy もう一方の入江
市川 イチカワ i-ot-i-ka-wa 獲物が群在する所の上手の岸辺
吉川 ヨシカワ i-o-si-ka-wa 獲物がとても多い上手の岸辺
日吉 ヒヨシ pi-i-o-si 石原の獲物がとても多い所
pi-o-us-i 石原の川口がある所
牛倉 ウシクラ us,i-kur,a 湾状の日陰
平井 ヒライ pira-i 崖の所
豊栄 トヨサカ toy-o-sa-ka 泥だらけの(川口の)前の上手、岡
稲木 イナギ inaw-ke 幣場、祭場の所
野田 ノダ nota/nutap 太地の頬/川の湾曲部
なお、設楽原の地名は下記のようなものではないだろうか。
設楽原 シタラガハラsi-tar-ka-para 大きな滝川の上手の広い所
新城宿から北上し、約25Kmで田口宿(現、設楽町)、さらに約18Kmで根羽宿に
付く。ここはもう一方の伊那街道、東海道の岡崎宿から上がる、足助街道とも呼ばれた合
流点であった。なお、田口宿のタグチ地名は下記のような地名であっただろう。
田口宿 タグチ ta-put,i 切り立った川口
設楽町 シタラ si-tar,a 大きな滝川
なお、根羽町周辺の地形は下記のようである。
図 4.長野県下伊那郡根羽村周辺地形図

根羽村 ネバ nay-pa 川辺の太地の頭、山
*稲武村 イナブ (昭和期に稲橋村と武節村とが合併して出来た。)
本郷 ホンゴウ ho-un-ukaw 川口にある石の重なり合い
梨野 ナシノ na-sinot 水辺の遊ぶ所、祭場
柏洞 カシワホラ kas-wa-ho-ra 越える岸部の山裾の低い所
夏焼 ナヤケ na-tu-ya-ke 水辺の山縁の所
矢作川 ヤハギ ya-pa-ke 山縁の太地の頭、山の所
取手 トリデ tor(=tur)-te (尾根が)伸びている所
鉢盛山 ハチモリ pachi-mor,i 鉢状の岡
萸野 グミノ kut-muy-o 岩崖の入江の川口
田島 タジマ ta-suma 切り立った岩山
檜原 ヒバラ pi-par,a 小石の川口
小戸名 オトナ (i-)ot-na 獲物が群在する水辺
茶臼山 チャウシ chasi 砦、祭場跡
売木峠 ウルギ ur-ke 峠の所
御所平 ゴショダイラko-so-ta-pira そこは岩礁の切り立った崖
さらに北北東へ約26Km、西に恵那山を見る所が駒場宿である。現在の長野県下伊那
郡阿智村である。甲斐の名将、武田信玄は三河野田城を攻略中に倒れて、帰路中に駒場宿
周辺で無くなったのだそうである。
駒場宿 コマバ kom-pa コブ山の山頂
阿智村 アチ (e-)at-i 太地の頭、山が群在する所
飯田藩の城下町、飯田宿はさらに約10Kmの所である。
図 5.長野県飯田市周辺地形図

気になる地名は下記の通り。
飯田市 イイダ i-pitar その(神の)小石原
兀岳 ハゲ pa-ke 太地の頭、山の所
権現山 ゴンゲン kom-ke コブ山の所
南の飯田市から見た山容は下記のようである。
図 6.長野県飯田市の風越山の山容カシバード撮影像
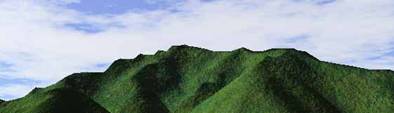
風越山 カザコシ kas-kus-i 上を越える所
市田 イチダ i-us-ta 獲物が群生する所
伴野 トモノ tom,o-nup 中間の原場、段丘
別府 ベップ pet-puto 川の川口
高松 タカマツ ta-ka-matu 切り立った上手の入り込んだ入江
八幡 ヤワタ ya-wa-ta 山縁の岸辺の所
松尾 マツオ matu-o 入り込んだ入江の川口
知久平 チクタイラ chi-ku-ta-pira 我らが水を飲む切り立った崖
駄科 ダシナ ta-si-na 切り立った大きな水辺
毛賀 ケガ kep-ka 削れた上手
殿岡 トノオカ tu-hon-o-ka 峰の中間のその上、岡
伊賀良 イガラ i-kar,a そこで曲がる所
高鳥屋山 タカトヤ ta-ka-tu-ya 切り立った上手の峰の縁
清内路 セイナイジ sey-nay-us-i 二枚貝/ホッキ貝の川がある所
平瀬 ヒラセ pira-se(ter) 崖の太地の背、瀬
飯田宿からは、諏訪湖を水源として伊那谷を貫通して遠州灘に注ぐ天竜川を遡る。伊那
谷の天竜峡は下記のような地名に相応しいのではないだろうか。
天竜川 テンリュウ ter-ruy 流れの踊りが激しい
さらに北上し、伊那部、高遠宿と進む。
図 6.長野県伊那市上伊那郡高遠町周辺地形図

伊那市、伊那部に関して下記のような地名が考えられるが。
伊那部 イナベ i-na-pet その(神の)水辺の川
inaw-pet 幣場、祭場のある川
inaw-pe 祭る所
ina-pet 火山灰の川
その他、下記のような地名が気になる。
高遠町 タカトウ ta-ka-tu-o-u 切り立った上手の峰裾がつき合う
箕輪村 ミノワ muy-o-wa 入江の川口の岸辺
御園 ミソノ muy-so-nup 入江の岩礁の原場
天狗 テング ter-kut 滝川の岩崖
権現山 ゴンゲン kom-ke コブ山の所
沢渡 サワンド sa-wa-un-to まえの岸辺にある沼
諏訪形 スワガタ su-wa-ka-ta 鍋底状の岸辺の上手の所
福島 フクシマ purke-suma 流れがゴボゴボ音がする岩山
野口 ノグチ not-put,i 出崎の川口
手良 テラ ter-ra 滝川の低岸
三峰川 ミト muy-to 入江の沼
美篶 ミスズ muy-sut-sup 入江の根元の激端
桜井 サクライ sa-kur-i 砂浜が日陰の所
春近 ハルチカ har-chi-ka もう一方の我らが上手、岡
ここは川を挟んで西春近、東春近と対にあ
る地名である。やや広域地名。
長藤 オサフジ o-sa-put,i 山裾が前に出ている川口(の所)
弥勒 ミロク muy-(pi-)rok 入江に石がゴロゴロとある
「弥勒菩薩は、未来に下界に降(くだ)って
仏となり、衆生(しゆじよう)を救うとさ
れる菩薩」だそうであるが、ここは仏教
用語の漢字の当て字であろう。
小原 オバラ o-par,a 山裾の川口
o-para 山裾/川口の広い所
勝間 カツマ ka-tu-oma 上手の峰にある
ka-to-moy 上手の池の入江
美和湖 ミワ muy-wa
入江の岸辺
三界山 サンガイ san-kay
前に出て壊れる
ここの東南の南アルプスは南に二列の火山
脈で出来た火山列であり、噴火により川が
塞き止められた地形であろう。
さらに天竜川を登り松島宿で両岸に分かれ岡谷道と分かれ、さらに登ると天竜川と分か
れて小野宿、塩尻宿とたどる。
松島宿 マツシマ matu-suma 入り込んだ入江の岩山
岡谷市 オカヤ o-ka-ya そこ(諏訪湖)の上手の縁/岸辺
小野宿 オノ o-no-o
山縁の尊い川口
塩尻市 シオジリ so-sir,i 岩/岩礁の山/土地
塩尻市の地形は下記のようである。
図 7.長野県塩尻市周辺地形図

ここでは下記のような地名が気になる。
今井 イマイ i-ma-i 獲物が群在する所
岩垂 イワダレ i-wa-tar-e そこの岸辺の滝川の入江
奈良井川 ナライ nar-i 高台の所
郷原 ゴウハラ ukaw-para 石の重なり合いの川口/広場
原口 ハラグチ par-put,i 川口
par,puti 共に川口を意味する。
小曽部 コソブ ko-so-p
そこは岩礁の所
ko-so-put
そこは岩礁の川口
太田 オオタ ota 砂場
桔梗ヶ原 キキョウガ key-ko-o-u-ka
山のそこで山裾がくっつき合う岡
平出 ヒラデ pira-te 崖の所
床尾 トコオ tok-o 突き出た山裾
鳴雷山 ナルカミ nar-ka-muy 高台の上手の入り込んだ所
洗馬 セバ sem(pir)-pa 日陰の岡
宗賀 ソウガ so-ukaw 岩礁の石の重なり合い
日出塩 ヒデシオ pi-te-so
石原の所の岩礁
霧訪山 キリトウ kir,i-tu-o-u
太地の足、山の峰の裾がくっつき合
う
ホッチ山 po-us-i 小山がくっついている所
ウトウ峠 ut-o-u 枝状の山裾がくっつき合う
ウトウ峠の山容は下記のようである。
図 8.長野県塩尻市のウトウ峠の北からの山容カシバード撮影像

上田 ウエダ ut-e-ta 枝状の山の所
ここもユニークな地形である。
長地 オサチ o-sat-i 川口が乾く所、枯れ川の川口
花岡 ハナオカ pana-o-ka 水辺の所、出崎のそこの上手、岡
塩尻宿から北へ約12Km行くと松本城下の松本宿である。かつて下記のような地名で
あろうことを論じた。
松本 マツモト matu-mo-to
入り込んだ入江の小さな池(の所)
* 印:カノ様の掲示板への投稿によりご教示いただいき、修正した。
ありがとうございました。