聖岳・光岳
2003 2/13
標高3,013mの我が国21位の聖岳は静岡県静岡市と長野県下伊那郡南信濃村境に
あり、白聖、奧聖、小聖岳などを従え、自らは前聖岳と呼ばれている。
図 1.北の赤石岳から見た聖岳の山容カシバード撮影像

右に兎岳、中央の聖岳からは左手前に奧聖岳、白聖岳と伸びている。山名の由来につい
て昭文社の「百名山」では「山頂の東南を流れる聖沢が肱を曲げたような形をしていて、
そのヒジルから転化した」と伝わっている説を述べている。「ヒジリ」山関係の山名は下
記のようにある。
表 1.各地のヒジリ山関連の一覧表
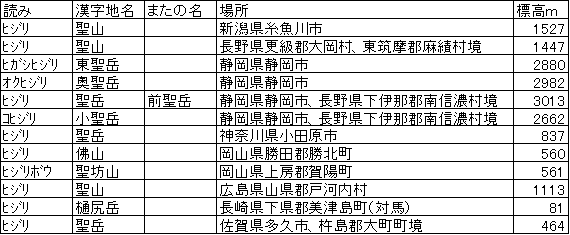
その他、長野県の聖山近くの聖高原も有名であり、文字からか、世俗を離れた高潔な印
象を与える。アイヌ・縄文語の立場から見ると下記のような山名に思える。
聖岳 ヒジリ pi-sir,i 岩/石の山
pi-us-ri 石が群在する高台
一方、南にある光(テカリ)岳は頂上付近の南西にやや下った所に光石と呼ばれる石灰
岩の石があり、その石に由来する山名との説である。
図 2.静岡県静岡市の光岳周辺の拡大地形図

アイヌ・縄文語の立場からは尾根の特徴を良く表した地名に思える。
光岳 テカリ te-kar-i そこで曲がっているもの、尾根
地形からは氷河により削れたカール地形の特徴を良く有している。イザルガ岳も以下の
ような地名であろう。なお、イザルケ岳とも呼ばれている。
イザルガ岳 i-sar-ka そこは/神の草原の上手/岡
イザルケ岳 i-sar-ke そこは/神の草原の所
一連の地形図は下記のようである。
図 3.長野県下伊那郡南信濃村、静岡県静岡市境の聖岳周辺地形図

聖岳も北西と南西にカール地形を成している。その他の気になる地名は下記のようであ
る。
シラビソ山荘 sirar-pi-so 岩盤の岩山の一帯
上村 カド ka-tu 上手の峰
立俣山 タテマタ ta-te-mak-ta 切り立った所の奥まった所
兎岳 ウサギ us−ke 湾状の所
なお、「ウサギ岳」に関しては下記のようにある。いずれも高山の堂々とした山で「ウ
サギ」のかわいらしいイメージと大きく違っている。
表 2.兎岳の山名一覧
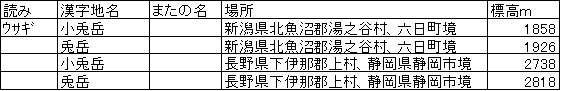
なお、兎平など「ウサギ」地名も各地にある。食料としての野ウサギが多かったことも
あろうが、上記のような地名と思われる。
椹島 サワラ sa-para 砂浜の広い所
鳥森山 トリモリ tur-mor,i 伸びている岡
上河内岳 カミコウチ ka-muy-ukaw-us-i 上手の山の石の重畳の地
上高地と同じ意味であろう。
笠松山 カサマツ ka-sa-matu 上手に開いている入り込んだ所
矢筈山 ヤハズ ya-pa-tu 山縁/岸辺の山の峰
加加森山 カガモリ ka-kar-mor,i 上手で曲がっている岡
易老岳 イロウ ir-o-u 一続きの尾根がくっつき合う
仁田岳 ニッタ nitat 湿地
仁田池がある。山頂の東北
茶臼山 チャウス chasi 砦、祭場
chi-as-i 我らが立っているもの
畑薙山 ハタナギ pa-ta-na-ke 山の切り立った水辺の所
大井川上流の畑薙湖、畑薙ダムがある。
青薙山 アオナギ o-u-na-ke 山裾がくっつき合う水辺の所