月山
2003 3/2
修験道の山として有名な出羽三山の主峰である。月山を中心に羽黒山、湯殿山の3山を
指し、先祖の霊魂が集う山とされ、「縄文文化はアイヌ文化に引き継がれた」、「アイヌ語
は縄文文化が小進化したもの」と主張される梅原猛先生も修験者の白装束の姿は死霊その
ものの姿であり、その形で死霊と関わるために向かう姿であると言われる。また、羽黒山
のクロはアイヌ語の「クル」、すなわち黒い死霊と関係する言葉であろう、と言われてい
る。確かに、「日陰」や「暗い」と言う意味と同時に「神」や「人」と言う意味もあり、
これらが混然となった言葉なのであろう。
図 1.山形県鶴岡市から見た出羽三山のカシバード撮影像

最高峰が月山、手前の左手に羽黒山、月山の右手に湯殿山があり、現在(羽黒山)、過
去(月山)および未来(湯殿山)の地理的な位置関係だけでなく精神的な意識と空間を行
き来することを意味しているのだそうである。昭文社の「百名山」では「頂上は実に広々
とした高原であった。小高い所に聖域月山神社があり、ここから南へ向かって緩い大きな
傾斜が気持ちよく延び、岩と高原食物に敷き詰められている。」とこの山の特徴を述べて
いる。また、地名の由来については「農業の神の月読命(ツクヨミノミコト)を祭ったこ
とに由来する。」、また別称の犂牛山(クロウシ)山について「遠くからみて牛が寝そべ
っているような山容から」とあり、別名の臥牛山のことを言っている。また、出羽三山と
も呼ばれていることを紹介している。
月山(ガッサン)の山名は以外に広がりを持って分布している。
表 1.各地の月山(ガッサン)分布
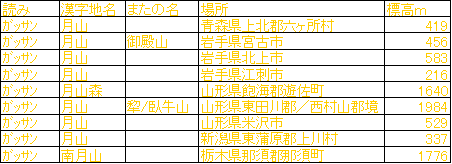
山の大きさも大から小まで様々である。漢字を当てはめた当時の人は意味の分からない
まま月の山と当てはめたが「ガッサン」と元々の読み方の漢字を「月山」に当てはめたら
しい。
ガッサンの地名の元の形を探るべく月山頂上付近の拡大図を見てみよう。
図 2.山形県立川町、羽黒町、西川町境の月山頂上付近の地形図

頂上付近に鍛冶小屋とあり、まさかここで鍛冶屋をやっていたものではないだろう。
カジという地名に「鍛冶」を当てはめたのであろう。ガッサンとカジから下記のような地
名であったのではと推定できる。他場所の月山の山名も納得できるのではないだろうか。
月山 ガッサン katu-san 形の良い寝そべった山
(katu:形、姿)、(san:棚のような平山)
と知里真志保の「地名アイヌ語小辞典」にあ
る。
鍛冶 カジ katu-i 形、景色の良いもの、所
なお、月山の地形図と共に周辺地名を見てみよう。
図 3.山形県立川町、羽黒町、西川町境の月山付近の地形図

この付近はかつての蝦夷文化圏であり、山中とあればかなり遅くまで弥生文化の影響を
受けにくく地名としてもそのまま残っているものが多いのであろう。
羽黒山/町 ハグロ pa-kur-o 太地の頭、山頂が陰になる山裾
羽黒山は414mの山であるがその南の
月山山系の直径の山系から1つ隔ててお
り、山頂といえども夕方には日陰になるの
が早い地理条件である。
立川町 タチカワ ta-at-ka-wa 切り立ったものがあちこちある上手
の岸部 日本語の意味と大差はない。
長坊山 ナガボウ na-ka-po-o-u 水辺の上手の小山がそこでくっつく
唐沢山 カラサワ kar-sa-wa 曲がって前に出た岸部
山頂の詳細図では山頂からZ字状に延びて
いる山裾があることが分かる。
藁田禿山 ワラタハゲ wattar-pa-ke 水辺の太地の頭、山頂の所
ワタラ の語順がひっくり返り、ワラタへ
柳沢山 ヤナギサワ yana-ke-sawa ヤナ棚の所の川
この山の周辺は本沢、赤沢川などに囲まれ
ている。
黒森山 クロモリ kur-moy 日陰の、暗い山
鷹匠山 タカジョウ ta-ka-so 切り立った上手の岩礁、または滝
品倉山 シナクラ si-na-kur 大きな水辺の日陰
姥ヶ岳 ウバガダケ upas-ka-ta-ke 雪の上手の切り立った所
小岳 オダケ o-ta-ke 山裾の切り立った所
千本松山 センボンマツ sempir-pon-matu 日陰の小さな入り込んだ入江
麓の念仏ヶ原の湿原などを表しているの
では
御城森山 ゴジョウモリ ko-so-moy そこは岩礁、または滝の山
なお、次の山名は後生のものと思われるがその意味を調べたので記す。
六十里山 旧六十里越は江戸時代には出羽三山の参
詣道として年間数万人が通行したとさ
れ、内陸部から約40kmの山岳道であ
り国道112号線の開通により役目を終
えたのだそうであるがなぜ60里なのか
は疑問として残る。なお、新潟県柏崎市
から福島県会津若松市までの約201Km
の国道252号線も六十里と呼ばれて
いる。
三足一分山 故事に因む山かと調べたが不明。
漢字の意味から3つの山で1体の山かと
考えたが、地形でもそのように思える。
なおここは朝日山系であり、アサヒ(a
s-pi:きり立っている岩山)、足のアシ(a
s-i:立っているもの)が山を指すことと
考え方として共通するのでは。
縄文時代からの山岳宗教との関わりを考えずには居られない場所であろう。